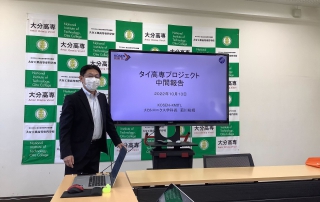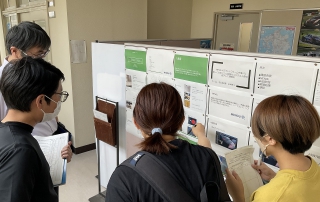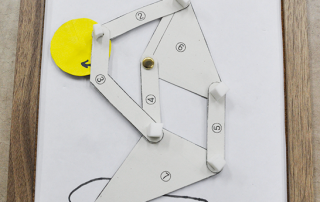タイ高専プロジェクトに参加中の菊川教授が一時帰国しました!その2
10月13日(木)に,タイのKOSEN-KMITLに勤務中の菊川教授が半年ぶりに帰国し,タイ高専プロジェクトの中間報告を行いました.タイの学校は日本と一か月ずれたスケジュールとのことで,現地高専が夏休み期間中での帰国とのことでした. 講義の内容に関する話から今後の展開,日本とタイでの文化の違いや生活の状況など幅広くお話しいただきました.現地は日本でいう所の1年中夏という事で,夏好きにはたまらない場所ですが,一方で1年中夏バテする可能性がある,と言われていたことが印象的でした.何をするにも健康が一番とのことです.